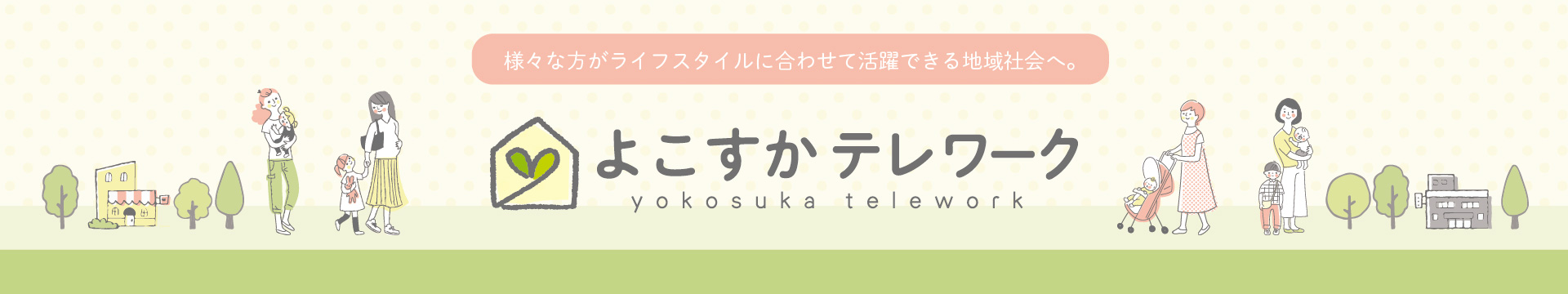障害児者やその家族にとって、暮らしていくためになくてはならない障害福祉サービス。
そんな障害福祉を支えるのは、普段利用している施設や事業所などの支援者や行政や関係機関。
そして、そのほかにも忘れてはいけない存在、それが市長をはじめ市議会議員や県議会議員の方々。いろいろな個人・団体から出された要望を受け止め、施策や制度に活かしていくその働きはとても大きいものです。

今回の対談のお相手である井坂しんやさんは、
- 障害者支援施設で3年勤務
- 横須賀市議会議員として16年
- 神奈川県議会議員へと着任して2年
福祉の現場での経験を活かし、議員になってからも福祉にかかわるさまざまな施策実現に向けて活動されています。
難しいと敬遠されがちな福祉や政治の話ですが、井坂さんのわかりやすい説明に加え、sukasuka編集部でも注釈をつけるなどして読みやすい対談記事を目指しました。どうぞ最後までご覧ください!
この仕事に就いたきっかけは?気になる井坂議員のこれまで
子どもの頃から身近だった障害福祉の世界
五本木 井坂さんは今、市議から県議になって活躍されていますが、政治の世界に入る前は障害福祉のお仕事をされていたそうですね。市議になったきっかけや経緯を教えていただけますか。
井坂さん 私は生まれも育ちも長沢で、母は『長沢学園』(現『三浦しらとり園』)の立ち上げの時からずっと保育士として働いていたので、私も小さい頃から長沢学園に出入りしていて、障害を持った方たちの生活に触れる機会は比較的多かったと思います。
清光ホームの職員として3年間勤務
井坂さん 大学では法学部に進み、教育法のゼミをとっていましたが、その先生が「障害の問題は人権の問題に必ず繋がる、基本中の基本だ」という話をされていたのが残っていました。
仕事に就く時には、学校の先生か福祉の現場で働くかという2つの選択肢がありましたが、たまたま武にある『清光ホーム』が新しく立ち上がるということで職員を募集していて、応募して働き始めたのがきっかけです。
ただ、ボランティアの経験もなく入ったので、まずは『三浦しらとり園』に2週間くらい研修に行き、そこで初めて「こんなふうにやるんだ」と知ることも多くありました。つまり、ど素人で福祉の世界に入ったというのが本当のところです。その『清光ホーム』では、支援員(当時は指導員)として3年働きました。
まさか自分が議員になるとは思っていませんでした
井坂さん 3年勤めた清光ホームを退職したあと、大学の時から入党していた日本共産党から「党の仕事をしてくれないか」ということで、半年ほど働き、その次の年に「選挙があるから立候補してくれないか?」と声がかかりました。政治に関しては、社会の先生になりたかったというのもあり、もともと興味があったのですが、まさか自分が議員になんて思ってもいなかったので、ちょっとびっくりしました。
議員の仕事ってなんだろう?施設で働いていた経験から見えてきた、やるべきこと
井坂さん 議員の仕事って、最初はあまりよくわからなかったんです。
だけど、障害者の施設で働いてた3年間のなかで「給与が上がらないよね」という話があって、そこで働いている人の給与が上がるには何が必要なんだろう?と考えた時に、そもそも施設の運営というのはどういうお金で成り立っているのか…というように次々と疑問が出てきたんですね。
普通の商売だと物を仕入れて売って、その収益で利益を得ていくわけですが、
- 障害のある方たちが生活をしている施設に対してのお金ははたしてどこから出てくるのか
- 当事者がお金を払っているのか、国が払っているのか…
- 清光ホームの運営サイドはどこからお金をもらって、どうやってスタッフに給与を支払うのか
そこが増えない限り、私たちの給与も増えないわけですよね。じゃあ何が必要かと考えたら、
- 政治の中で福祉のほうに回すお金を増やさないといけない。
- そういう仕組みを作っていかなきゃいけない
というのが、議員になって最初に思ったことです。自分が清光ホームに勤めた経験がなかったらそういう視点は持っていなかったかなと思います。
子育ても介護もどちらも大変。福祉のなかでお金を取り合っても意味がない
井坂さん 今は特に子育てのことがすごく注目されています。子どもが少ないし、子どもを持ちたいと思っていても持てない状況が作られているというのが背景にあるので、子育て支援をがんばりましょうという話になるのですが、一方で介護も本当に多くの方が悩んでいる状況ですよね。
福祉のお金を高齢にばかり使って子育てに使っていない、という言い方をされることもありますが、私はそれは間違っていると思っています。福祉に使われる資金が変わらない中で、お金の取り合いをすることには意味がないんですよね。
要は、福祉の資金枠を広げないといけないので、それを広げるには福祉じゃない別のところから持ってくるしかない。こういうのをやめて、こっち側に持ってきたらいいんじゃないんですか?という視点・発想が必要だと思うんです。
それで介護にも子育てにも、障害にも生活保護にも予算が行き届くようにするというのが、大きく見た上での政治の役割だと思っています。
福祉のことばかり見ていても駄目。全体を見てお金の流れを把握することが必要
井坂さん だけど、単に福祉に回すお金を増やすと言っても、
- そもそもどこからお金が出ているのか
- それをどんなふうに使っているのか
- どういう仕組みに基づいて報酬を出しているのか
ということがわかっていないと具体的な提案や主張ができません。ほかの分野のこともわかっていないと、「これ抜けるでしょ?」「これ要らないでしょ?」ということが言えないんですよね。そういう意味では福祉のことだけをずっと見ているだけではだめなので、福祉以外の分野についても勉強が必要になってきます。
全体を見ながら、どこを優先するかで議員さんの立ち位置が変わってくるんだと思います。
市議で16年、県議にきて2年ちょっと。政治の世界にかれこれ18年
井坂さん 県議に移ったきっかけは、単純に共産党の県議が1人もいなかったからで、横須賀で県議をとりたいという党の方針によるものです。
横須賀は中核市(※詳細は後述)ですから、県がやっている権限を市のほうでやっていることが多い。そういう意味では「わざわざ県に行くというのはどうなの?」と思うところはありましたが、そうは言いつつ、もちろん県の重要性もあるので、そっちに行く人もいなきゃいけないという思いはありました。
・・・
障害者施策の歴史はまだまだ浅い!?めまぐるしく変化する制度のこれからが気になる!
『知的障害』という言葉が使われはじめたのは1998年。それまでは『精神薄弱者』だった
五本木 今回の対談の前に自分なりに予習してみて、障害者に関わる制度や施策がちゃんとできたのは本当に最近のことなんだということに、ちょっとびっくりしました。特に、『知的障害』という言葉ができたのが1998(平成10)年で、それまでは『精神薄弱者』と呼んでいたというのが、ちょっとショックでした。ついこの間ですよね。
井坂議員 やっぱりそういうふうに受け止められていたということなんでしょうね。『国際障害者年』あたりから少しずつ、呼び方も変えようという流れになったんだと思います。
身体・知的・精神の3障害。なかなか同じように理解を進めるのは難しい…
井坂さん 施策についていうと、3種の障害がひとつになって、そこからいろいろと新しくなっていったという流れがあります。
身体は比較的わかりやすいですから、昔から横須賀にも盲学校やろう学校はありました。
また、後天的に障害をもった人たちは、自分自身の障害について自分で勉強し、知識を得て、権利を主張できる方も多くいましたので、こちらも比較的早く施策が進んできたという部分があります。
でも、知的はやっぱり自分で主張を伝えられないところも多いし、外から見ただけでは軽度か中度かわからないということもあるので、周囲の理解がなかなか進まなかったのかなと思います。
精神については、施策の面では本当に遅れていますから、まだまだ、3障害が同じような段階にあるとは言えませんね。
[ターニングポイント・その1]法改正で措置から契約へ
国や市町村が持つべき責任が制度の変化により契約者本人に
五本木 いろいろと法改正もありましたよね。
井坂さん 2003年に支援費制度が入って、措置から契約へ変わったのはひとつの大きなポイントだと思います。
措置も、良いところと悪いところがあったと思います。
措置の場合は基本的には全部公的機関が責任もちますよということだったのが、契約になると本人たちの責任になるので、責任の所在が変わるんですよね。
そういう意味では、自分個人としては、公的機関、国や市町村がちゃんと責任を持つべきだというふうには思っていました。
ただ措置では自由度がないじゃないかという見方も確かにありました。
- 施設も少ない
- グループホームみたいな日常生活の場も働く場も少ない
- そういう中で行政のほうに来た人にはこのぐらいはできますよとやっていたというのがそれまでのことだったんですよね。
契約になって良かったのは、
- ちゃんとサービスが必要だと言った人にはそれだけのサービスをちゃんと支給しよう
という動きになったこと。
そしたら、あまりにも利用者が増えて、支給が大きくなりすぎてパンクしちゃったんですけどね。こんなにお金がかかると思っていなかったんでしょうね。
自立支援法になって起きた反対運動
それから3年ぐらいで自立支援法ができて、また一割負担を入れるというので大反対が起こりました。
当時、自立支援法の負担のあり方に対して裁判をしていた方々を民主党が応援していましたが、実際に民主党政権になった時にその方向でちゃんとやってくれないから、「あれ?おかしい!」ってことになって、自立支援法が廃止となりましたが、今の制度はそれをほとんど引き継いだものになっているのが問題なんです。
現場はどう変わった?サービスの需要が増え、提供者も増え、書類も増えた!?
五本木 一連の法改正によって、障害の現場ではどんな変化を感じましたか?
井坂さん 契約になったことで、現場では書類が多くなったと思います。
それから、サービス提供者が増える方向にはなったと思います。サービスを受けたい人が増えれば、仕事をやろうという人も増える。需要と供給の関係ですよね。
同時に、事業所に対する監査だとか設立認可だとかの仕事が市のほうでは増える。そういう意味では業務が増えたんです。
サービスが広まったことには一定の評価。でも複雑になりすぎた制度には疑問
井坂さん それだけサービスを受けたいという人が増えたってことではあるので、まったくなんでもかんでもマイナスだったかと言われると「サービスを受けてもいいんだ!」という流れができたのは良い部分としてあるのかなという気はしています。
ただ、負担の割合や考え方が変わったことははたして良かったのかどうかという疑問は残ります。
今でも、契約に変わったことがいいことだとは思っていません。サービスを受けている方にとっても、制度がどんどんどんどん複雑になって、わけがわからなくなっているのが現状です。
五本木 確かに自分たちも、サービスを受ける段階で契約書を読み上げてもらうのを聞きながら、「あ、はい」と返事をしながら、実のところ、あまり理解はしていません。
井坂さん 誰か制度を理解している人が契約をしてくれるのは確かに便利ですが、「それでいいの?」という思いもあるので、すごく迷います。
一方で、その当事者が制度やサービスを、しっかり選択できるだけの情報量と判断する力があるかというと、それもどうかなと思っています。
つまり、任せっきりは良くないというところと、どういうふうにしたら自分の生活の中で必要なサービスを受けることができるのかな?どんな形がいいのかな?というところは、良いところも悪いところもあるので難しいですよね。
[ターニングポイント・その2]横須賀が中核市になったこと
県から権限をもらうことでさまざまな役割を担うように
井坂さん 横須賀市にとっては、中核市になったことが大きな転換ポイントです。
市町村合併をして市町村に渡すお金をあちこちに分散させず、まとめることで財源を減らす政策のひとつとして国が進めていたのが『大都市制度』で、これには政令市・中核市・特例市があります。
横須賀市はそれまで条件が合わなかったのが、その条件がどんどん緩和されて、2001年に中核市になり、それにより神奈川県から福祉の制度も含めた色々な権限をもらうことになったんです。
加えて、その後の地方自治法の改正によって、例えば介護の事業者の認定や障害のサービス事業所の認定など、色々な仕事の権限も県からもらうことになりました。ただ、そうすると今度は、そこに対する監査を持たなくてはいけないというようなことも生じてきました。
いくつか制度の違いもあったので、そういう一連の仕事が横須賀市にきたということは、障害福祉の行政を進める上では1つの大きなポイントだったと思います。
『サービス等利用計画』の作成が義務化され、仕事量が莫大に
井坂さん そして忘れてはいけない、『サービス等利用計画』を作らなくてはいけなくなったことも、もう1つの大きなポイントだったと思います。それまでは、「可能なら作ったほうがいいよ」というのが、「全員作らなければいけない!」となったのは2015年、本当につい最近のことですよね。
五本木 そうですね。私たちの子どもたちがひまわり園に通園していた時、ちょうど切り替わるタイミングだったと思います。
井坂さん これは法改正の時だったので猶予期間がありましたが、3年間で全部作らないといけないと言われて、最初は施設入所者からのサービス等利用計画を作って、それを徐々に広げて全員分作っていくというかたちになったと思うんです。
だから、最初は「その計画を作ってくれ!」とか「サービスを受けるにはどうしたらいいのか」という相談は、市の職員の人たちがほとんど全部を受けたんじゃないんですか?
そのうち、4ヵ所の相談支援センターができて、相談を受けるところが増えましたが、最初のうちは市の職員の人たちに相当な荷重があったと思います。
五本木 そうですよね。計画書作成の負担が大きすぎるというのは今現在もかなり問題視されていて、横須賀にある4つの相談支援センターも、プランを作る仕事量が増えてしまって、本来の仕事が回らなくなってしまっていると聞きました。
井坂さん それは本当にあります。全員作らなければいけないとなったことが原因にありますが、「できるだけ作る」で良かった頃は、「じゃあ、支給量どうやって決めるの?」と言われたら、やはりほとんどの方が市の窓口に相談に行っていたので、市の職員さんはそれはそれで大変だったんじゃないですかね。
利用計画はセルフプランの人が多い現状…。費用負担に課題あり
五本木 今、利用計画はセルフプランの人もとても多いですよね。流れとしては、支援センターできちんとつくってもらいましょうという動きにはなっていますが、実際に数は足りていないので時間がかかる、それならば自分で…という。
井坂さん 計画を作って、計画的にサービスを支給するのは必要なことだと思うんです。
- ただ自分で作るのは大変。
- でも誰かに頼むとなったら、その人が仕事として成り立つだけの費用負担が発生しない限りは難しい。
- じゃあ、それは誰が負担するの?利用している人たちなの?それでいいの?
という話になるわけです。ただでさえ障害年金が少ない中で、それで暮らさないといけない人たちが、
- はたして計画相談にお金を払うの?
- この人はそれで本当に生活できるの?
ということを考えると、やっぱり公的な部分が負担するという制度にしない限りは成り立たないんですよね。
介護の場合は、ケアプランを作ってもそれでやっていけるんです。具体的には、
- 1人当たりの作成量の上限が決められている
- 毎月プランを作って見直しをするので、1ヵ月サービスを利用してみてどうだったかを見ながら必要に応じて変えられる
利用者ひとりひとりと話をして、プランを作成して、見直して…という時間を考えると、ちゃんとケアプランを作って運用できる数ということで37人という制限があったと思います。1人あたり1日2-3人程度ということになりますね。
介護保険の後を追っている障害福祉。事業として成り立つには利用者の絶対数が必要
五本木 福祉の制度というのは、イメージ的には介護保険の後を追ってるという感じでしょうか。
井坂さん はい、完全にそうです。
五本木 介護保険といったらケアマネさんがいて、相談してケアプランを作ってもらって、利用するところに繋げてもらってっていうのが、もうかたちとして出来上がっていますよね。それを今、障害福祉の方にまるごと移そうっていう感じですよね。
井坂さん そうですね。ただ、介護のほうがサービスを受ける人の絶対数が多いんです。そうすると事業として成り立つからサービスを提供する側も一定量ある。
それにひきかえ、障害のほうは、どういう支援が必要かもそれぞれ違うし、絶対的な人数がそもそも少ないので、事業者が成り立つかという課題をいつも抱えていると思います。
横須賀はまだいいほうだと思いますが、例えば三浦で同じようにサービスが成り立つかと考えると、単独ではたぶん難しいんじゃないかな。
サービスを利用できる場所も限られてしまうので、相談に行ってもなかなか利用に繋がらない。そういう意味では、事業者自身で成り立つかを考えると、ちょっとあやふや。だから結局、介護と障害のサービスを両方やるっていう事業所が増えているんですね。実際、国のほうも、最終的には一緒にしていくっていうところを目指していると思います。
株式会社の参入が増えるも、商売にならず撤退してしまうところも。人口の少ない地方ではどうやっていくかが問題
介護や障害の事業所は、今はやっぱり株式会社が入ったりとかしていますが、結局、つぶれてしまうところも多い。人口が密集しているところは比較的商売になっても、密集していないところは商売にならないから、やらないんですよ。
そうなると、地方の介護や障害のサービスというのはどうなっていくのという問題が出てきて、最終的には公的な所が責任を持たなければいけなくなってくるんですよね。そういう意味で、公的な責任を少なくしていく今の流れでは、今後、弊害はたくさん出てくると思います。
介護・医療・障害をひとつの制度にしよう、という国の流れがある
だから医療と介護と障害を全部1つのものにしようと、そういう制度に国も向かっている。
介護には今、株式会社が入れるようになっているので、次は医療に株式会社が入れるようにしていこうという動きが進むわけです。このままいくと、
- 国保も含めて医療まで国の負担がどんどん縮小
- 自己負担分が多くなる
- 自己負担が増えないようにサービスを抑える。
という制度が全部、同じ形で進むようになるので大変だなと思っています。
実際、今、アメリカでそういうふうになっている仕組みが、規制緩和だとか国際戦略とかそういうのを1つの足がかりにしてそっくりそのまま日本に入ろうとしていることに、自分は不安を感じています。
規制緩和というと、いいように聞こえるけれども、たとえば株式会社が参入できないという規制を外して商売させていく方向になるわけで、実は必要だった、今までみんなの暮らしを守っていたような規制を壊しているところも非常に多い。
障害もそういう方向にいくとなると、本当に「えっ?」って思うじゃないですか。だけど、介護も医療も障害も繋がってはいるんです。結局、国が目指そうとしている方向を見ていくと、「本当にこのまま進んじゃっていいの?」と思います。
議員としてこれからやっていきたいことを聞いてみました!
五本木 井坂さんが、議員としてこれからやっていきたいことはなんですか?
井坂さん 挑戦したいことはたくさんありますが、今は県会議員としてできることは何でもやっていきたいと思っています。
- 福祉の問題でいえば、やっぱり3障害のうち精神のところを引き上げていくためにはどうしたらいいのかということ
- 医療や介護にしても、みんなが本当に必要な時にお金の心配なしに使える制度にしたい
と思っています。
制度を作る=法律を作る、これが議員の仕事!
法律を作るのは国会議員だったり県議会議員だったり市議会議員なので、やっぱり基本的にはそこを目指したいなと思っています。
暮らしていくなかで困難はたくさんあるんだけれども、不安をできるだけ解消して、安心感が持てる、そういう社会にしたいなぁと。ここはこういう制度があるから大丈夫、ここはちゃんと面倒見てくれるよとか、そういうふうになるといいなと思っています。
本当は、先に述べたような方向に国が進もうとしてるのを止めたいと思いながら、止めきれずにずっときてるので、最後の砦だけはしっかり守っていきたいなという気はしています。その砦が守れたら、次は変えていけるキッカケになるんじゃないかなぁって思っています。
みなさんに伝えたいこと…必要だと思ったら絶対に必要だと言い続けて!
井坂さん それぞれの分野で取り組みをしている方たちに必ずお伝えするのは、必要なものは必要だと言ってほしいということ。
いろいろな団体から出てきた要求の中で、できることを考えるのが政治家の仕事です。要望を受け止めてしっかり考えるのが議員・市長・知事・それから職員の役割だと思っています。
だから、どんな要求があるのか、こういうふうに思っている人がいるということがわからないと、動けないんです。だから、そこはちゃんと言ってもらった方がいいかなと思います。
・・・
政治の世界は本当にいろんな分野で繋がっているし、お金の使い方も広く見ながらになりますが、ただ、それぞれのところで深くそうした問題を感じてる人たちがいるというのが大事。1人で全部!というわけにはいきませんが、私たちも力を合わせて頑張っていくしかないと思っています。
sukasuka-ippo代表・五本木愛の視点
井坂県議会議員と初めてお会いしたのは今年の4月。福祉の繋がりでご紹介いただいたのをきっかけに、いろいろなお話を伺う機会がありました。
今の障害福祉の制度って?難しい言葉がたくさん…正直よくわからない!
実際、私たちのような幼少期の障害児を育てている保護者は、
最近では、去年の4月に『障害者差別解消法』が施行され、それによって『合理的配慮』が行政機関や事業者に義務付けられたことが話題になりましたが、なんとなく耳にしたことはあっても具体的にはよくわからない、という方も多いのではないでしょうか。
難しそうな言葉が並んでいて読んでもよくわからないから、つい敬遠してしまう…。私も以前はそうでした。
現状を知り声を挙げる…難しく考えずに、保護者目線の率直な意見でいいと思います
ひとつひとつの用語や政策を勉強した上で個人で要望を出すというのは正直、難しいかもしれません。
ですが、保護者同士のコミュニケーションの中で、普段困っていることについて他の人はどうしてるんだろう…と疑問に思うことなどを情報交換してみると、自然と「こうだったらいいのに」という声は出てくるのではないかと思います。
「受給者証ってどうやったらもらえるの?」
「デイサービス、通ってみてどう?」
「移動支援、どうしてる?」
そんな身近な話題も施策を知るきっかけになりますし、自分が感じている不便は、なにか改善する方法があるかもしれないという視点を持って、次の行動につなげていくこともできると思います。
先輩保護者との関わりも大事!
また先輩保護者の方々が団体や親の会主催で行っている勉強会や講演会なども、私たち幼少期の障害児を育てる親にとって、分からないことを分かるに変えるチャンスになります。
先輩保護者の方々も、折に触れ、私たち幼少期の親の声を集める機会を作ってくれています。
そんなことを意識して参加すると、アンケートの記入があった時には、ただ感想を書くだけではなく、自分の困りごとをちょっと書き添えてみるなど、そういう関わり方も不便な現状を変えるひとつのきっかけになると思います。
・・・
私たちが今さまざまなサービスを受け暮らすことができているのは、これまでの施策の歴史があってこそ。これからの横須賀をもっと暮らしやすくしていくために、やはり私たち当事者が現状を把握し、足りないことや必要なことなどを声としてきちんと挙げていくことが大切だと改めて感じました。
そしてそれを受け止め変えていくことが行政の役割だとおっしゃっていた井坂さんの言葉を、とても心強く感じました。
井坂さん、
またぜひ、別の企画でもお話を聞かせていただきたいと思います。
・・・
2017.07
取材/五本木愛・pototon・ゆかねこ
写真・加工/pototon
テープ起こし/kayoko・ゆっぴー・がらっぱち・kyoko
文・構成/yuka kaneko
編集/ takeshima satoko
sukasuka-ippo
最新記事 by sukasuka-ippo (全て見る)
- 【イベントお知らせ】~障がい児とその家族の交流の場~2024年度『すてっぷ』活動のご案内 - 2024-05-09
- \今年も販売やります!/『令和5年度障害者週間キャンペーンYOKOSUKA』のお知らせ - 2023-11-28